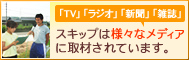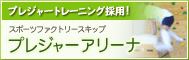指導者講習会 2
プレジャーアリーナで月末特別レッスンを済ませ、岐阜市体育指導委員連絡協議会主催の岐阜市体育指導委員全体研修会での講演の為、岐阜市北部体育館へ向かいました。
 久しぶりの雨で足元も悪い中、多くの先生方がお集まりになられ私もいつものことながら緊張・・・。
久しぶりの雨で足元も悪い中、多くの先生方がお集まりになられ私もいつものことながら緊張・・・。
 人生の先輩方を前に講演するのは何度経験しても慣れる事はなく(どの講演でも緊張するのですが)しどろもどろな2時間でしたが、先生方は熱心にペンを走らせたり、話に耳を傾けていました。
人生の先輩方を前に講演するのは何度経験しても慣れる事はなく(どの講演でも緊張するのですが)しどろもどろな2時間でしたが、先生方は熱心にペンを走らせたり、話に耳を傾けていました。
 どの地域でも指導者の前向きな姿勢に、逆に感心してしまいます。
どの地域でも指導者の前向きな姿勢に、逆に感心してしまいます。
市民体育室の山田先生には何度となく連絡を頂き、大変ご迷惑をおかけ致しました。また、いろいろな手配をして頂き大変お疲れでした。