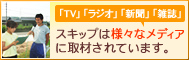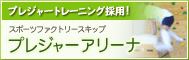決め付けは危険
「うちの子はこれが苦手なんです。」 「この子にそんな事を言ってもわかりません。」 親御さんは我が子の事を理解しているかようにレッスン中におっしゃられる事が多々あります。
本当にその通りなのでしょうか?
過去の経験や本人の性格から判断しての助けだと思いますが、その言葉がお子様の成長を著しく制御してしまう事さえあります。
「僕はできるのに・・・。」「私の事ちっともわかっていない・・・。」
お子さんは内心こんな思いをしているかもしれません。
大人の勝手解釈で決め付けてしまうのは非常に危険です。反抗というプレートが跳ねあがる前にお子様をいい意味で疑って下さい。