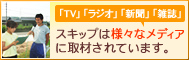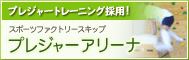スポーツにおいて「フットワーク」という言葉をよく耳にします。 辞書では「球技・ボクシングなどで、足の運び方。足さばき。」となっています。
バランス・リズム・連動(体を巧みに操る)など、のプレジャー感覚が必要となってきます。
ボクシングに例えてみましょう。
3分間を戦うためのスタミナはロードワークで蓄えますが、足踏みやパンチを出すための踏み込みやジャブの連打などは「リズム」。
横・前・後ろなどにステップを踏む時に必要な「バランス」。
相手にパンチを正確にミートさせる「連動」。
思わぬところからパンチが出た時に瞬時の判断で避ける「切替」。 相手との間合いを保つ「距離」。
など、これ以上にもあげられ「感覚」は様々です。
フットワークはゲーム的要素の強いあそびや競技には必要不可欠で、子ども達のあそびの代表としては「鬼ごっこ」。TV番組では「サスケ」や「東京フレンドパーク」などがあげられるでしょう。
 中川区・冨田教室にて。
中川区・冨田教室にて。
マットと跳び箱を置いて溝に落ちないように走り抜ける設定をしました。
子ども達は自分のスピードに合わせながら次の目的地まで「距離」を測りジャンプします。走りながら踏み切り足を調節(リズムを合わせて)してジャンプ(連動)し、着地(バランス)後に次への目的地まで走ります(切替)。
 少し跳び箱をずらすと跳び箱のトップではなく横を蹴ってすばやく次へ駆け抜けます。
少し跳び箱をずらすと跳び箱のトップではなく横を蹴ってすばやく次へ駆け抜けます。
この発想ができるとTV番組に似てきますよね。
何も言わなくても子ども達は色々な失敗経験や成功経験から進化を遂げていきます。
これらに飛んできたボールを避ける。高いとこにあるタンブリンをたたく。などの付加価値を付け加えるとさらにフットワークの練習になりますよ。