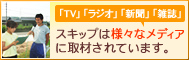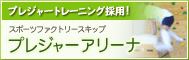平常心ではない と思わないといけないのでは?
あおり運転の報道や、野良ネコ・野犬にエサを与える報道を見ない事がない昨今、常識では考えられないアンビリーバボな事が目に映ってしまう。
子どもの行動ならまだしも大人が堂々と行う。
昨日、久しぶりの休みを利用してバイクに乗ったが、無理な追い越しをしてきた車が障害者マークをつけていたり、自称90歳のお父さんが1人でドライブしていると話しかけてきた。
ハンドルを握ると、どうしても気が大きくなったり運転が上手と思ってしまったりする。それは老若男女、健常障害関係なくみなぎる感情なのでしょう。
自分が引き下がるのも身を守る術の1つと考えなければならないのでしょうね。
TrackBack URL :
Comments (0)