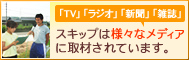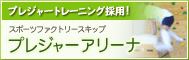「基礎」から「応用」への転換期
今日の個人レッスンでのこと。1桁のかけ算はすんなり答えれるのですが、1桁×2桁となると途端にストップしてしまうお子さんとの根性比べでした。
例えば、5×9 はわかっても、 50×9 は別物なのです。
始めは言葉クイズとして口頭だけで出題をしていましたが、紙に書いて出題しても難しいようでした。
私たち大人は過去の経験から「応用力(いたずら心)」を勝ち取り、今も利用し続けていますが、子ども達にとっては「基礎」から「応用」に転換することが難しい時期にぶつかる時が今後も多くなると思います。
逆に、昔のイメージでの教育方法では(今の教育綱領が完全に理解していない為にこのように書かせていただきます)、学年が上がるにつれて「応用」ばかりになる為に「基礎」ができない子はもちろん、基礎を活かしきれない子もますます取り残されてしまう傾向にあります。
私の場合、5年生で英語を習い、6年の私に月謝が高いとの理由で塾をやめました。中学になり1学期までは100点でしたが、2学期になった矢先に塾で習ってない過去形や進行形に突入し、あっという間に落ちこぼれとなりました。高校になれば英語に限らず苦手な数学もわかるだろうと思い、胸弾ませて登校しましたが、中学の延長・・・。むしろ難しくなっている(当たり前ですが)。
会員様のお母様との話の中で、「訓練をさせなきゃ」とおっしゃられました。その通りで、学校の宿題とは別に100枡計算やパズルなど、勉強に関係ないことがむしろ重要で、その積み重ねが基礎と応用をつなげる架け橋になると考えます。
過去に出来たから今日も出来る。これが出来そうだからこれも出来るだろう。よく私達も憶測の中でレッスンを発展させていきますが、いきなりの応用はタブーです。やはり基礎を十分に行なったうえで、応用への糸口やヒントをワザとらしく見せたり教えたりしながら、後は自分で勝ち取っていく進め方を考えています。