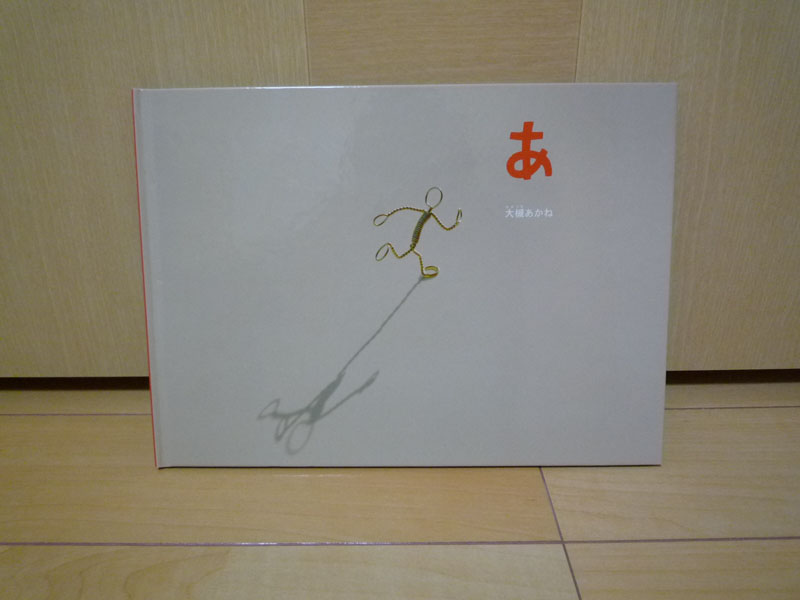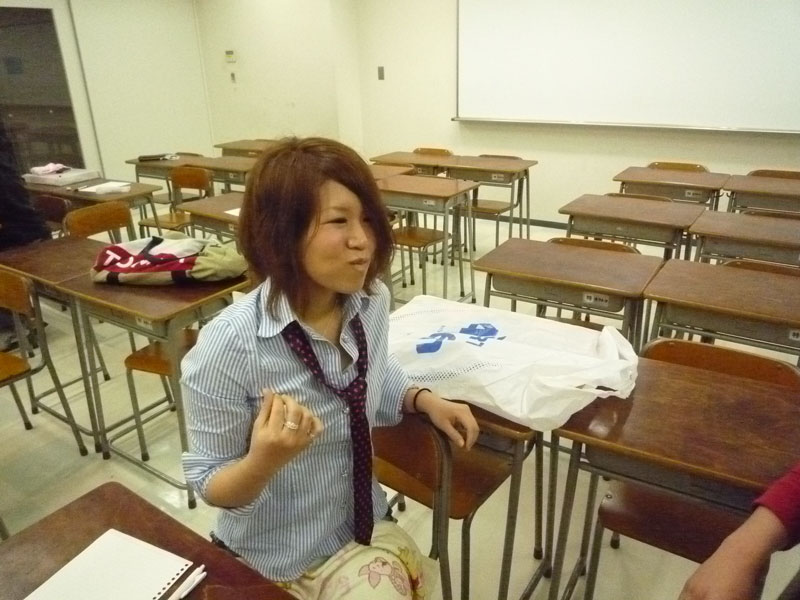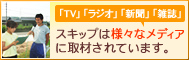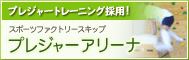今日は少し難しいお話を・・・。
スキップの運動療育レッスンにも参考とさせてもらっている「感覚統合療法」の解説を文献を元に解説します。
例えば「りんご」がテーブルにあるとします。皆さんはそれを目で見て見たり手で触ったりして「入力」という行為をします。
りんごからは甘いにおいがしたり、赤い色だったり、つるつるしていたりといういろいろな感覚刺激が出ています。それらは脳の中に入って、過去に「りんご」ということばを知ったこととか、食べた経験など一緒になります。そして、出てくるのが「りんご」ということばや食べるという運動ということになります。我々の生活はこれらが何度も繰り返されています。
そして、この「現在の感覚刺激や、過去の経験や記憶」を「感覚統合」といいます。
つまり入力からのいろいろな感覚刺激と脳の中の記憶などの情報を1つにまとめて行動を決定するわけです。
では「感覚統合に問題がある」とは、入力は一般的には誰も同じです。しかし、出力がちょっとおかしい、ことばや運動がおかしい場合がそれです。しかし「障害児は誰でも皆、感覚統合に問題があるのか」というとそうではなく、
一次性感覚統合障害=学習障害(LD)・幼児自閉症etc 機能系の障害
二次性感覚統合障害式色盲・聾・脳性マヒetc 機能の障害
例えば、目が見えない・耳が聞こえない・また脳性マヒのように身体にマヒがある方の場合は、「入力」の時点で他とは異なっています。ということは、「出力」がおかしくても仕方ありません。ところが、感覚統合療法を受けている子ども達は、ほとんどの子が目はちゃんと見えているし、耳もちゃんと聞こえているし、身体にもマヒがない。「入力」には異常がない。それにもかかわらずことばが遅れていたり多動だったりと「出力」がなんだかおかしいのです。
つまり二次性感覚統合障害は、機能が悪いために二次的に感覚統合の障害を起こしているのです。彼らには問題のある機能を補ったり代償したりすること、例えば目が悪ければメガネや点字を、耳が悪ければ補聴器を脳性マヒ児はマヒに対しての訓練を行うことになります。
しかし、一次性感覚統合障害の子ども達は、どこが悪いのかわからない。結局、機能ではなく機能系が悪いのではないかという仮説が生まれます。
車で例えると、「バッテリーではなくコードがどこか変になっている」と考えるとわかりやすいかもしれません。
スキップでは、療育レッスンを受けている会員様に対し、様々な刺激を与えていけれるようにスタッフ共々考え続け、時には勉強させてもらいながら課題提供しております。
参考文献
・感覚統合ミニ実践研修会資料 京都大学作業療法学
・おかあさんのための感覚統合療法 旭川荘療育センター療育園 若松かやの