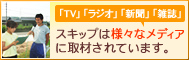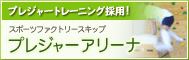じぶんでしようとするこ
「願う子どもの姿」の2回目。
「じぶんでしようとするこ」
・守られている中で、自分でやってみようとする。
・励まされる中で、意欲的に挑戦しようとする。
・繰り返し行うことで、自信がつき挑戦しようとする。
・自分で「できた」という満足感を味わうことで、頑張ろうとする。
・あそびや生活の中で考えて行動したり、自分に思いを伝えたりする。
・「やればできる」という成就感を体験することで、すぐ諦めないでやってみようとする。
失敗を恐れていると何もできません。たくさん失敗すればいいんです。大人も子どもも、自分でスイッチを押す事で達成感が味わえます。「挑戦スイッチ」がたくさん押せる子ども達に育てていけるように、スタッフ達は常に考えています。